コラム
睡眠時無呼吸症候群、改善の基本は減量!
睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に呼吸が止まる疾患で、日中の眠気、頭痛、身体のだるさ、集中力の低下など日常生活に支障をきたす様々な症状を引き起こします。この記事では、睡眠時無呼吸症候群の基本から、予防や改善に役立つ運動の効果について解説します。
睡眠時無呼吸症候群とは
睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に何度も呼吸が止まる疾患です。医学的には10秒以上息が止まる状態を無呼吸といい、平均して1時間あたり5回以上の無呼吸が見られる場合に診断されます。睡眠の質が低下することで日中の眠気、頭痛、体のだるさなどの症状を引き起こします。
また、血液中の酸素が欠乏することで、心臓・脳・血管に負担がかかり、脳卒中や心疾患などの重篤な合併症を起こす危険が高まります。高血圧症や糖尿病などの様々な持病への悪影響も確認されています。

主な症状
睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に発生するため、本人の自覚が難しくなります。睡眠中に頻繁に目が覚める、起床時に頭痛やだるさを感じる、日中の眠気を感じる、周りの人からいびきや無呼吸を指摘されるなどの症状があれば、早めに専門医療機関を受診しましょう。
- 急性期:大きないびき、夜間の頻尿、起床時の頭痛やだるさ、日中の眠気など
- 慢性期:高血圧、不正脈、糖尿病、認知障害、発育障害、うつ状態など
主な原因
睡眠時無呼吸症候群の原因は、空気の通り道(上気道)が狭くなる閉塞性と、脳から呼吸の指令が来なくなってしまう中枢性の2種類に分類されます。中枢性の発症メカニズムはまだ完全には解明されていませんが、一般的に多くみられる閉塞性には以下のような要因が挙げられます。
肥満
体重が増えると首周りに脂肪がたまって気道が狭くなり、呼吸が止まりやすくなります。
加齢
年齢が上がると筋肉が弱まり、気道が閉塞しやすくなります。
その他
鼻炎・鼻づまり、扁桃腺肥大、飲酒、睡眠薬の使用など
運動の作用と効果
睡眠時無呼吸症候群の予防や改善には、適度な運動が非常に効果的です。
減量・体重管理
適切な運動と食事管理によって体重を減少させて首回りの脂肪を減らすことで、気道を広げて呼吸がしやすくなります。適度な筋力トレーニングとウォーキング、ジョギング、サイクリングなどの有酸素トレーニングが効果的です。
呼吸筋の強化
喉の周りの筋肉を強化することで、気道が閉塞するのを防ぐことができます。特に、口呼吸を減らすトレーニングや舌や喉を使ったエクササイズが有効です。
睡眠の質を向上
運動によって体温が上昇し、その後の体温低下が眠りを促進します。また、運動によって睡眠ホルモンのメラトニンの分泌が促され、質の良い睡眠が得られます。
ストレス解消
運動はストレスを軽減し、自律神経が整うことでリラックス状態を作り出します。心身のリラックスは睡眠時の無呼吸を減少させる助けとなります。
まとめ
睡眠時無呼吸症候群は日常生活に大きな影響を与え、高血圧や心疾患のリスクを高める可能性があります。しかし、運動習慣を身につけ、体重管理をすることで予防や改善が可能です。
メディカルパーソナルジムシープスでは、医療機関と連携して個々の健康状態に応じた安心安全なトレーニングを提供しています。睡眠の質を改善して心身の健康を守るため、運動によって睡眠時無呼吸症候群の予防や改善に取り組みましょう!皆様からの体験のお申し込みをお待ちしております。
監修
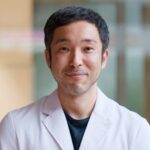
星加 義人
(ほしか よしと)
- 医学博士
- 日本内科学会 認定内科医
- 日本呼吸器学会 専門医
- 日本医師会 健康スポーツ医
呼吸器内科の専門医として、順天堂大学医学部附属順天堂医院・呼吸器内科勤務や越谷市立病院・呼吸器科医長などを経て、2016年に草加きたやクリニックを開業。
何でも気軽に相談ができる地域のかかりつけ医として、生活習慣病をはじめとした病気の予防と改善に力を入れている。
筆者

中山 雄大
(なかやま ゆうだい)
- 全米ストレングス&コンディショニング協会 ストレングス&コンディショニングスペシャリスト
- 全米ストレングス&コンディショニング協会 パーソナルトレーナー
- 日本スポーツ協会公認陸上競技コーチⅠ
中学から陸上競技に取り組み、社会人時代に400mハードルで富山県記録を樹立。その後、自身の経験を活かして富山県総合体育センターでジュニアアスリートのトレーニング指導に従事。
現在は、幅広い層の方々の健康体力の維持・向上に貢献し、健康的な生活を実現できるように専門性を活かしたサポートを行っている。
